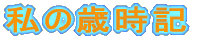
つくも・さとみのエッセイ
もくじ
〈いのち〉
01 小さないのち
02 奪われるいのち・失われるいのち
03 宅間死刑囚の死刑執行
04 暴力のこと
05 死刑のこと →→→《《以上のページ⇒リンク》》
06 ふたたび死刑のこと→《《⇒ページ》》
07 <反日>に思う →→《《⇒前のページ》》
08 〈恐怖〉のこと(⇒このページ)
▲ 「件」という妖怪の話 → リンク》》》
▲ 「妖怪論」 →→→→ リンク》》》
08 〈恐怖〉のこと(「反日」から)
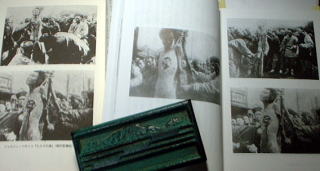
↑バタイユおよび村瀬の本から
驚くべき一枚の写真
あの、亡母が語ってくれた「政治犯の処刑」の話は、はっきり「政治犯」と名指されたものではなかった。
私は、その話を忘れがたく、長い年月を過ごした。
そして、1992年(それを買ったときのメモがあるのでわかるのだが)、ぐうぜん村瀬学の『恐怖とは何か』という本に出会った。
その冒頭に、中国(北京)の「1枚の恐怖の写真」という節があり、村瀬は書き出しをこう書いていた。
<こんな恐ろしい写真を私はそれまで見たことがなかった。
身も凍るようなと形容されるのは、こういう感じのことを言うのだろう。>(村瀬学『恐怖とは何か』)
その写真をみたのは、20年ほど前(だから1970年代はじめということになる)だと書く。そして、村瀬はこの1枚の写真をジョルジュ・バタイユの『エロスの涙』で見たという。そして、バタイユの文を引用して、
<「この写真は、私の人生において、ある決定的な役割を果たした」
今になってあらためて思うのである。そうか、この写真はバタイユにも衝撃を与えていたんだと。>(〃)
だが、私もそれと似た写真をどこかで見た記憶があったようだし、これと同じように衝撃的な写真を見たとも思える。
これは、1905年に撮影された北京での政治犯の公開処刑で、生きたまま「百刻み」にするという残酷な死刑であった。村瀬は、次の小節でこう書いた。
<こういう光景は、おそらく古代からくりかえしくりかえし見せつけられてきた状況ではなかったか。いわゆる「みせしめ」としての処刑である。ここには集団を支配する権力者の「力」の示し方がある。…>(〃)
それはまったくそうなのであるが、こういう残酷さは原始・古代において宗教儀式ではありえても、「みせしめ」刑罰としてあったのかどうかは断定できない。残酷刑は、むしろ中世から近世において「発達」したのかもしれない。
その一例として、わたしも加わった地方史の調査研究でもこの百刻みの刑は「壱分刻ミ」として記録されていた。
ともかく、私はこの写真をあの上海の話と直結させてしまったのである。
もともと《恐怖論》と、地方史研究と、母の話とがかさなって、この村瀬の本を躊躇なく買った記憶がある。
バタイユは
ところでバタイユはその最後の著となった『エロスの涙』に、この「中国の処刑」の同じ場面の写真を5枚掲載した。このうちの1枚をバタイユは持っているとかいてもいる。
<この写真は、私の人生において、ある決定的な役割を持った。私は、この恍惚的(?)であると同時に耐え難い苦痛の像によって付きまとわれることをやめなかったのである。>
(G.バタイユ『エロスの涙』私が参照しているのは2001年初刷のちくま学芸文庫である。)
たしかこのバタイユの衝撃と苦痛は、近代西欧の知に特有のものだと思う。西欧において、中世期にいかなる残酷刑が行われてきたか。中国のこの写真の処刑は、時間をずらせば西欧のものでもあるだろう。
そして何よりも、ニホンでは1945年の終戦まで、アジア各地で行ってきた「みせしめ」のための刑罰としてむしろ親しいものである。
これが、ニホンの外だけではなく、日本の国内の処刑として公開でみせつけてきたものと大して変わりはない。写真だからこそ、衝撃が強いともいえるが、村瀬が言うように、
<…ナチスの強制収容所での死体の山、ベトナム戦争中、爆弾に吹き飛ばされ、頭と足だけになったべトコン兵士を、ボロ布をつまむようにつまみ上げているアメリカ兵の写真など、それこそ山のように見ることができてきた。…>
のに、なぜニホンの軍隊や政治犯の公開処刑などが問題にならないのだろうか。それが不思議でさえある。
なお、バタイユの『エロスの涙』に「解説」を書いた林好雄という人は、
<その写真のことは思い出したくなかった。その本は捨てたと思っていた。>
だが「解説」を書くいま
<自分の書棚にその本を見つけたときには、驚愕した>
などと書く。ほんまかいな、と私などは思う。
私はといえば、これを探したが、見つからずがっかりしたのである。だいたい、どんな理由であれ、本は捨てるべきものではない。「その本」に憎悪するなど特別の感情があるなら、捨てずに図書館に寄付するか、欲しい人にあげればいい。寺山修司が「書を捨てよ」といったのは比喩である。
焚書は、権力の行為である。