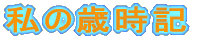
つくも・さとみのエッセイ
もくじ
〈いのち〉
■01 小さないのち ■02 奪われるいのち・失われるいのち ■03 宅間死刑囚の死刑執行
■04 暴力のこと ■ 05 死刑のこと (以上このページ)
■06 ふたたび、死刑のこと (⇒次のページ)
■07 <反日>に思う (⇒リンク)
■「件」という妖怪の話》リンク》》》
■「妖怪論」 》リンク》》》
<いのち−05> 死刑のこと
政府の「世論調査」
先日、マスコミが「死刑制度」に関する内閣府の世論調査の結果を報道した。
あくまでも「内閣府の世論調査」であるから、設問自体から疑ってかかる必要があるが、報道は、
<死刑容認 初の80%超>
ばかりを強調した。
調査は、「基本的法制度に関する世論調査」で、2005年2月19日に内閣府が発表した。(中国新聞05/2/20 以下引用は同じ)
それによると、
死刑制度を容認する人が 81.4%
(1975年調査では最低記録56.9% 前回1999年調査70.3%)
死刑廃止を求めたのは 6.0%(2.8ポイント減)
この調査は、奇妙なもので、
刑事事件への関心の有無では「ある」が91.7%
…そのうち関心がある犯罪種別(複数回答)は
「窃盗、詐欺など財産に関する犯罪」が52.0%、
強姦、強制わいせつなどの性犯罪が 31.2%と大幅に増加した。
(なお、調査全体では対象者数3,000人、回収率は68,3%で非常に低い。有効回答者比率は不明)
などと、報道している。発表そのままで、まったく批判力を感じない記事だ。
およそ、犯罪に関心がない人は珍しいので、刑事事件に関心がある人が91.7%(回収率を考えるとわずか60%にすぎない)は数字としては少ないとも読める。「ない」と答えた人は、調査自体に批判的な人で、たぶん言われるとおりに調査に応じたくなかった人の数だろう。
そのうえ、複数回答で、各種刑事犯罪への関心は、いま、マスコミで大々的に報じられているもの(「振りこめ-おれおれ」詐欺、奈良の小学生拉致殺害事件など)なのに、わずか約半数から3分の1のポイントしかない。
しかも、犯罪被害者への直接取材ラッシュで、その被害者の感情は当然とはいえ(それでも、場合によって直接的な感情の露出が気になることがある)、あまりに露骨な報道合戦がある、中でのこと、である。
おそらく、この調査があたかも何の犯罪にも関係がないような仮構のイノセントぶるステージで行われるから、たとえば性犯罪に「非常に」関心があるとは回答しづらいことも理由の一つだろう。つまり、設問と回答とその報道すべてが一つのフィルターを通したフィクションに近いのだ。
調査そのものの分析が必要な調査である。
それにしても、死刑制度の容認の%が異常に高い。
ここでも「世論」が権力とマスコミの共同作業でつくられている、としか見えないと思う。
「世論調査」ならぬ「世論操作」である。
(この点、姜尚中+テッサ・モーリス・スズキ『デモクラシーの冒険』が参考になる)
「求められる冷静な視点」!?
それでも、「中国新聞」は、「解説」をつけ、「求められる冷静な視点」と書いた。その中で、死刑廃止を訴えているアムネスティ・インターナショナル日本のコメントを掲載している。
「不安に駆り立てられた状態での数値だ」
「死刑が有効に犯罪を抑止する証拠は得られていない」
「事件をセンセーショナルに報道されるため、治安が悪くなったように感じてしまう実態がある」
かなり、カットされた文である。
わずか、これだけだが、まずマスコミ自身が「冷静な視点」と「報道」を目指すべきであろう。冷静とは思えない報道を繰り返しているのは誰か? と、私は言いたくなる。
まあ、こう言ってみても「仕方ない」かあ、と、思うばかりだ…。
実はこの「求められる冷静な視点」は、「2009年までに国民の参加による裁判員制度も始まる中、犯罪被害者の人権保護を含め」のあとにつづくフレーズなのだ。何が言いたいのか?わからない気分。玉虫色とはこういう色だったか?
嘆息せざるをえない。
日本史上の死刑廃止時代
日本史上の「奇蹟」とも呼ばれる死刑廃止の時代があったことは存外知られいないように思える。
26代の天皇、347年間、3世紀半の長きにわたって死刑が行われなかった時代がつづいた。
724年(神亀2)聖武天皇から、保元の乱(1156年)で、後白河天皇側の平清盛が、崇徳上皇方の平忠正とその子4人を斬首にするまで。これが、ふたたび父子兄弟で血で血を洗う死刑史のはじまりとなった、と言われている。(参考・森川哲郎『日本死刑史』日本文芸社)
いまNHKの大河ドラマ(義経)が、その戦乱の時代の「英雄史」をとり上げているのは皮肉といえば皮肉だ。
その著、森川哲郎『日本死刑史』に、「八海事件」など多くの冤罪事件の弁護士をつとめた正木ひろしが「同志・森川君のこと」こう書いている。(本書は現在入手可能かどうかわからない。)
<本書は、昔から、権力の座にあった階層が、合法を装った刑罰の名によって、どのような残忍な死刑を実行してきたか、それを歴史的に回想するすることによって、その根が深く、かつ広く、現代にまで及んでいる事実を反省させようとしているもののように思われる>と。
著者・森川哲郎は、
「死刑制度を中心に、殺す者、殺される者の歴史は悲惨であった。」
「歴史は死刑残酷史の首塚である」という一側面も忘れてはならない…
と、書いている。
事実、冤罪による死刑、正義を名のる死刑、異教徒の殺戮、大量虐殺などの残酷史は、まさに目を覆いたくなるほどだ。
この残酷さは、世界史上似たようなものらしいが、モンテスキューは
「『法の精神』で日本を最も残酷な死刑を行う国として、しばしば例にあげている」という。
いまだ、自虐史観などといって日本の戦争責任を不問にし、「歴史をつくる」会とか言っているが、わずか半世紀前、日本が国内外でいかに残虐な殺戮をしたか、忘れるのはあまりにもひどい。人殺しをその方法で比べるのはどうかと思うが、戦争による殺戮と死刑はどんな殺人よりも残酷である。
記憶に残るのは、たとえば、血が滴るような中国人の生首を手にぶら下げ、日本刀を持った兵士が、誇らしげに記念写真に写っているものがある。それは、まぎれもなく私たちの父・祖父の世代である。
それどころか、つい最近も「市中引き回しの上、死罪にしたらいい」と大臣が言う、これが現実である。
私は、歴史教科書に、そういう写真も紹介し、残酷な死刑の歴史も教えたらいいと思う。
よくも、ここまで人は残酷なことを思いつくものだと、おぞましくなる。
<いのち−04> 暴力のこと
はっきりさせるべきは・・・
いま、殺人事件がマスコミをにぎわせている。
いつの時代も、殺人は「時代社会」の悲惨なおわり(結末)と悲劇のはじまり(因縁)として繰り返されてきた。
近年、インターネットが関係する事件が目立つ。
私たちもネット社会の一員として積極的に発言していきたい、と重たい気分で思う。
インターネットも含めて、時代の犯罪や傾向について発言する精神科医や心理学者は多いが、彼らのほとんどは、専門的に責任をもつようなものではない。発言も、みんなほとんど同じことを言う。わたしはバスジャック事件のとき、それまで比較的信頼できると思っていたMaという精神科医が、
「外泊を認めた医者が悪い!」と叫ぶのを見聞して驚いた。個人的な怨恨があっても、マスコミで言うべき問題ではない。
こうした中で、香山リカは、くっきりとした「りんかく」が見える主張と思考を示すことができる貴重な存在である。
私は、香山の発言すべてに賛成ではないが、現在では、マスコミに登場する中でいちばん信用している。
香山リカの近著『生きづらい<私>たち』も注目できる。
そこには「専門」の苦悩と模索、体験と思考が示されているから、私のド素人の発言とあわせて読んでいただければ幸いである。
ところで、本題であるが、少年や、若者の殺人、また、大人から高齢者までの事件も、一見別問題かに思える他方で行われているイラク戦争やテロリズムや殺戮も、殺人に至る暴力としては、まったく同じ意味を持つことをはっきり言っておきたい。
いかに、アメリカが自分の軍隊が行っている暴力を「正義」といい、テロリストが自分たちこそ「正義」だと言おうと、それは、同じ行為である。その戦争は同じ暴力である。
一説に戦争は暴力の中で正しいものだから、テロが最悪の暴力だ、という学者がいる。
えっ?!とびっくりするが、そんなことはない。戦争はそれを正当化する者たちが「ルールに基づく正しい暴力だ」と主張するだけである。暴力、殺人に正義も不正義もない。
イラクやあちこちの戦争とテロ、暴力とを認めておいて、個人や集団で行われる暴力・殺人をべつものとするのは、最初のまやかしに過ぎない。
戦争は「犯罪」である
戦争の中に、なにか「犯罪行為」とそうではないものがあるわけではない。
戦争自体が、重大な犯罪である。
このさい思い起こすのが、ガンジーの言葉と教えられたこと、「平和への道はない。平和が道である」・・・公人としてのガンジーの評価は別にして、考え方は示唆的であろう。
暴力と「言葉の暴力」はまったくちがう
小学生が同級生を刺し殺した事件は記憶に新しい。加害少女は、被害者が(なんども?)自分の悪口を「ネットの掲示板」に書き込んだから殺した、とその動機を述べたらしいことが伝えられた。
これを、まず、そのまま信じておくとして、なお、はっきり言うべきことは、
「暴力と、言葉の暴力はまったくちがう」
ということである。
しばしば、暴力を否定するのかしないのか、わからないようなことをいう人々は、言葉の暴力と肉体に及ぶ暴力を同一のものと言う。
そんな無茶な話はない。
その違いは、言葉の暴力は被害者が反論する余地はありうること、また、加害者も、間違いを認め、訂正、謝罪ができ、わずかでもつぐないができる(可能性がのこされている)ことだ。
ところが、肉体的・身体的暴力は「とりかえし」がつかない。
DV、セクシャル・ハラスメントなどでも、それが精神的苦痛にとどまるものか、肉体を損傷するものか(もちろん双方に及ぶのが当然でもあるが)、はっきりさせるべきことなのである。
そこをアイマイにすると、言葉の暴力を身体・肉体的暴力に発展させる論理を否定できない。
言葉から暴力へ向かうことをとどめ、ブレーキをかける論理が失われる。
おおくの「暴力の実際」において、強いものが相手を抑圧するのは「言葉」によってではない。
けっきょくは、物理的な暴力の発動である。
「ペンは剣より強し」という言葉も、ペンと剣を対極に位置づけ、比較することによってのみ成り立つ。
いいかえれば、ペンとペンの「たたかい」では、権力(暴力装置)は常に勝つことにならないのである。つまり、権力の基本的な志向である永続追求が否定される。権力を倒した暴力は、また、同じ権力に落ちる。
どこでまちがったのか
「言葉の暴力」と言う、その言い方(論理)が最初の間違いである。
「暴力的な言葉」と、どうちがうか。
「暴力的な言葉」という言語表現は、言葉と暴力をいちおう別物とする意味をもつ。
ところが「言葉の暴力」は言葉=暴力という前提がある。
言葉のなかに暴力とそうではないものがある、という意味が混同されている。
さきにとりあげたように、戦争には「犯罪ではない」ものと「犯罪であるもの」がある?!という考え方の間違いと同じことだ。
暴力にも犯罪(あるいは間違い)と、そうではないものがあるわけではない。
暴力は、どんな暴力も間違いであり、犯罪である。
安直な議論に、外科手術も暴力であるように、「正しい暴力」がある、という言い方がある。
外科手術は「物理的」「身体的」であるが、いつもそれが暴力であるとはいえない。
なぜか? 手術は相手を意図的に傷つけること自体を目的とはしない。その目的と手段が双方によって承認されていることが前提だからである。
イラクでの戦闘で目に傷を受けた少年が、にほんで手術を受けるために来た。その手術は、テロと同じ暴力だ、あるいはアメリカ軍と同じ武力の行使だとだれが思うだろう。そのたぐいの議論は空しい。
では、暴力が双方によって承認されていれば同じではないか?
そう、戦争がその最大の行為である。
他にも、まれにそういう事例がある。その典型が「(故)宅間死刑囚の死刑」である。
この場合、死刑の執行(命令者)と、死刑で死んだものとが暴力を共有した。
だから、私は、それを「共犯」と言ったのである。
その「犯罪」は死刑囚の動機をも共有した。人間として「たちなおりたくない」という動機である。
この共犯「事件」は、ニホンにおける法治主義と「民主主義」の歴史に明記すべき「犯罪」である。
あの、小学女児同級生の殺人事件と酒鬼薔薇聖斗少年の事件に共通するのが、暴力否定の論理が混乱していた点である。
前者が「言葉」と「暴力」、後者が「ゴキブリや野菜」と「人間のいのち」の混同であった。
実にいたましくも、わたしたちの社会全体が責任を負うべきことであると思うのである。
そのことは、わたしたちに「暴力の徹底した否定」を求めているのではなかろうか。
<いのち-03>宅間死刑囚の死刑執行
なぜ?宅間守の死刑は早々に執行されたのか?
高村薫は「宅間死刑囚 異例の早期執行」(現論・中国新聞04.11.7)に「透明性欠く制度運用」という見出しで、コラム記事を書いている。
「今回の異例の執行について、法曹界は三つ理由を挙げる。一つは再審請求の可能性がないこと。一つは本人が死刑を望んでいること。そして一つは世論の支持である。しかし、本人の抗告取り下げなどで刑が確定し、再審請求の可能性がない人はほかにもいる。また本人が死刑を望んでいても精神状態を理由に、四半世紀以上も未執行の人もいる。そして「世論の支持」であるが、国民がいつ、宅間死刑囚の刑を早く執行しろと言ったか。」
これが、中ほどに置かれた高村の論の要旨にあたると読んでいいだろう。
だが、わたしはもし、これが「法曹界」の見解であれば、もはやそこに「法の適正な執行」を期待しない方がいいと思ってしまう。
「民主主義の行政は、とにかく定められた手続きをとことん行うこと」
つづいて、高村はこう書く。
「仮に国民がある憎々しい犯罪者を早く殺せと言っても、国がそんな一部の感情に従うことはあり得ないし、あってはならないだろう。それが法の運用というものだと国民も考えているから、法には一応従うのである。」と。
「世論の八割が(死刑)制度を容認しているからといって、国民は制度の恣意的な運用を認めているわけではない」。
「確定した刑の執行は法律の解釈ではなく、あくまで事務的な手続きである。」
もし、「世論」によって法の執行を行うのなら、死刑も国民投票によって執行しなければならないだろう。「世論」などというものは、どうにでも「解釈」できるのだから。
そしてこう結ぶ。
「宅間死刑囚は例外だったというのなら、」「法務省はその旨をはっきり言うべきである。いや、言えるものなら言ってみるがいい。」
きびしい調子だ。
だが、「民度が低い」などという例に従えば、ニホンの「政治度」「法曹度」が低いのは、今にはじまったことではない。
「恣意的な法の執行は、憲法違反においてとっくに、合法とされている」
くどいような引用をしたが、その必要を感じた。
だが、高村はなぜ「ここ」だけに問題を狭め、イノセンスを決め込むのだろうか。
恣意的な法(そのもっとも基礎的なものが憲法、国際法であるが)の執行は、実に「イラク派兵」など枚挙に暇がないほどひんぱんに行われ、それが「合法」とされているのだ。そしてそれをうらづけるのが世論である。
この「世論」が、たとえばTVなどの放送局が発表するとき、いつもNHKが現政権に有利な数値を示すのも面白い。仮に宅間死刑囚の死刑執行についてアンケートをとれば、「賛成・やむをえない」が多数になるに違いない。
わたしも、死刑の執行が、
「時々の法務大臣や官僚の都合で左右されてはたまらない」と思う。
「制度の恣意的な運用」はゆるされることではない。
「繰り返すが、わたくしは現行法で確定した刑が執行されることに異存はない。」…
しかし「なぜ宅間死刑囚の執行だけが確定から一年未満の早さだったのか。そこに、誰もが理解できる順当な理由はあったのか。わたくしは「なかった」と思う。」
高村は書いている。
高村は「死刑制度の存廃論議」について、態度を表明しない。いや、死刑制度に反対はしないのである。
その論議に「一長一短があって、現状ではこれで万全といった結論は見出せないし、広く国民の間で議論が高まっている状況でもない。」と。
高村は、無論のことかもしれないが、中山千夏や辛淑玉らが、死刑廃止と「おんなを法務大臣にするな」と訴えていることには触れない。(「おんな組いのち」)
「死刑の廃止こそ」
ならば、高村はいつごろ「万全といった結論」がでると見るのか。
仮にまんいち明日、結論が出たとき、もし、死刑は廃止すべきだということになったら、高村は何か言うことがあるのだろうか。
あえてわかりきったことを理路に添って言うならば、すでに死刑制度は施行されているのだから「存廃」ではなく「廃止」の議論があるのである。「存」ではなく「廃止・反対」の意見がある。
高村はそのどちらでもない、というのか?
また「国民」云々というが、死刑制度が廃止されず、逆にこの件のように「恣意的な運用」をされても、とくに厳しく追及されるということも「ない」のである。これは「民度が低い」ことを示す。
高村という作家は、思慮深そうな感じだが、中途半端に「考え込む」から、意見も中途半端になると思えるフシがある。つまり「恣意的な運用」をする側には、まあこれぐらいなら…と見られていることを怒りを込めて書いているのだ。
高村は、何におびえて思考を途中で自己規制するのだろう。
人の命を奪うことこそもっとも恐れるべきだとわたしなどは思うのだが。(2004/11/09)
<いのち-02>
奪われるいのち・失われるいのち
イラクで、パレスチナで、各地のテロで、戦争で、犯罪で・・・いかに多くの人命が奪われているか、思うだけで気分がふさぐほどだ。
ことに、今年のニホンでは、台風や水害、地震などの災害で多くのいのちが失われた。新潟中越地震では、多くの人が「まさか!ここで」と驚いたことも伝えられた。
災害列島に住むかぎり、いや、地球全体が、逃げ場のない星なのだと言える。台風や地震では、高齢の死者が多かったのも切実な問題だろう。
最近、記憶に強く刻んだできごとがつづいた。
ひとつは、中越地震で母子3人が生き埋めになった現場から「奇跡的に」救出された3歳の子、その救出の瞬間は涙が出るほど感動的だった。だが、非情にも4歳の子と母親は亡くなった。中越地震のひとつの象徴的なできごととなった。
ある青年の死
また、イラクでテロリストに殺された一人のニホン青年。香田生証さん。
その死について、あるイラク人医師は日本人支援者におよそ次のようなメールを送ってきた。その医師は、今年、半年を名古屋で研修をうけ、8月に帰国したばかりだという。そのメールが公開された。
彼はこの「誘拐・殺害事件の背景」を、「イスラム教の指導者たちの調整がまったく機能していない」最悪の事態だという。
その原因は、
「ほとんどの指導者が刑務所に送られ、残りはイラク国外に逃げてしまったこと」。
「イラク国内には、アメリカのための軍隊か、テロリストしかいないんです。」
「もうイラクに日本の人を送らないでください。バクダッドで私たちはより困難な生活を送っています。」
と、ますます悪化する現状を訴える。悲鳴のようなメールである。
彼は、「日本人が自重してイラクから離れること」
「日本軍の早期撤退をお願いし」「彼らの命も守ってください」と書いている。
くわしく引用したいが、直接ごらんになるほうがいいだろう。
BBSにHPのURL(アドレス)を書き込むので、そちらを参照していただきたい。
terrorist BUSH
テロという場合、「国家テロリズム」を除外するのが普通になっている感があるが、
terror(テロ)/terrorism(テロリズム)/terrorist(テロリスト)
は、語義としてとうぜん恐怖政治を含むので、
bushをterroristと見るのもまた当たり前だ、とわたしは思う。
実際問題として、たとえばファルージャで、銃撃戦をしているアメリカ軍と武装勢力とをあちらが軍隊でこちらがテロリストと区別しても、当事者同志では180度意味(敵か味方か)が違うが、第3者には意味がない。
武器を使って他者を殺す者か、武器を持たず他者を意図的に殺そうとはしない者か、の違いだけだ。軍隊は、明らかに味方ではないものをすべて敵と見なす。
いまアメリカ合衆国は、terrorが支配する国だということは、このたびの選挙がみごとに証明した。人々は、おのれの不安と恐怖から逃れるために「悪の枢軸」というフィクション・ストーリーにもとづく「戦争」つまりbushの「正義」というフィクションを選んだ。
民主党候補との僅差という結果も、すでにアメリカン・ストーリーのシナリオになっている。 (04.11.09)
<いのち-01>
小さないのち
「卵」
いのち、というものを実感できる場面は多いのかもしれない。
でも、なにか大きく構えるような話ではなく、ささやかなことで感銘することがある。私は、まったく瑣末なことに自分なりの発見に出会う体験をした。
なにか、ここに書くのも気恥ずかしいが、ひとつのナマ卵を割って、その見事な形状に、その卵を産んだ鶏を思った。(この卵は、ある若い女性が―家族や多くの人々の援助はあるのだりうが―ひとりで営んでいる農場で、放し飼いのとりが産んだものだ。
それはともかく、にわとりの卵の澄み切った白味、円形の黄味、そのはりのある、やわらかな暖色、見事だ。そして、それは美味しい。多少は飼料が与えられるのだろうが(ずっと昔のとりが貝殻を与えられていたように)、そこらの草やたまにはミミズなども食べるだろう、そうした珍しくもない食べ物だけでも、鶏は美しい卵を産む。そんな食べ物で、毎日、見事な卵を産む。これは感動的なことだ。
その餌になる草もすばらしい。
「草」
この夏、庭の草をとりながら、思ったものだ。いったい、取ってもとっても生えてくるこの草たちは、なにを養分にしているのやら。水と太陽と空気と土に含まれるわずかな栄養分。それらが、こんな不思議な形をした、際限なく生える生命力をつちかっている。いのちのシステムというか、造化の不思議。
そして、草にまぎれるように生きている小さな虫たち。
ミミズもたくさんいた。
「蟻」
たとえば、蟻。
何を食っているのか、つぶさにはわからないが、黒光りがする蟻たちは、忙しそうに庭のあちこちを歩き回る。
そのシステムはよくはわからない。ただ、つくってみよ、と言われても、おそらく人間誰一人も、ただ1匹の蟻とて造ることはできない。同じ形をした機械や装置はできても、それはしょせん「ぜんまいじかけの」ロボットあるいはナノテクノロジーがつくった偽者でしかない。
そうした些細なことの、端々で、<いのち>について思った。そして、多少は皮肉っぽく、いのちがおのれの<いのち>自身に感動することがまれでもあることを。(2004.11.01)