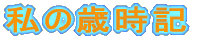
つくも・さとみのエッセイ
もくじ
〈いのち〉
01 小さないのち
02 奪われるいのち・失われるいのち
03 宅間死刑囚の死刑執行
04 暴力のこと
05 死刑のこと → 以上前のページ》》
06 ふたたび、死刑のこと(このページ)
07 <反日>に思う(⇒次のページ)
▲ 「件」という妖怪の話 → リンク》》》
▲ 「妖怪論」 → リンク》》》
06 ふたたび死刑のこと
[追記2] 「第二の宮崎、宅間に」
昨2004年11月、奈良市内の小1女児誘拐殺人事件で逮捕された小林薫被告(36)の初公判が、4月18日、奈良地裁で開かれたとマスコミは大々的に報じた。被告は、8つの罪状を全面的に認めたという。
<「第二の宮崎勤、宅間守として世間に名前が残ればいい。(死刑判決を受けて)早くこの世とおさらばしたい」…>(中国新聞2005.4.19)
検察官は、供述調書をこのように読み上げたと。
ただし、弁護人は、それは
<被告の「本心ではない。情状鑑定や被告人質問で心理状況を明らかにしたい」と述べた。>
とも伝えた。
被害者遺族は、やはり「死刑以上の刑罰」を求めたという。
被告の供述書をそのままほんとうに思ったこととしても、「名前が残ればいい」という価値基準は、どうして被告のものとなったのか?まず疑問である。どこかで、「名前が残」ることが、殺人と死刑に値すること、という教育・教唆があるはずだ、と思うのだ。それを明らかにしなければ、供述書の信憑性も疑わしい。
しかも、「第二の宮崎勤、宅間守」である。被告は、この二人の殺人者についてどのような知識があり、なぜそう思うのか?疑問は強い。
そして、検察とマスコミは、法的に関係のない別の固有名詞を出したのだから、これだけでは彼らを単に利用したことになろう。
なぜ?宮崎や宅間なのか?そのことを明らかにする責任がある。宮崎も宅間もすでに刑に服したのだ。そのことを思え!
[追記] 死刑以上の…!
最近マスコミで、殺人などの被害者家族から「死刑以上の思い罪を」という言い方をよく聞くようになった。やはり、感情をとどめきれない思いだろうことは否定できないが、ものごとを感情のレベルで決定することは避けたいものだ。
もし「死刑以上」の刑罰があるとして、たとえば江戸時代の残虐刑が想起されているのなら、家族を含めて死罪などということになる。
だが、もう一つの方向は、死刑ではなく、「生きて罪をつぐなう」ことが可能である。
ニホンでは、刑罰に対する意識に江戸時代から明治、そして今日へとひきつがれてきた「復讐」と「見せしめ」があると思える。これは、ぜったいに被害者家族のもとめに応じたものではなく、あくまで、統治者の思想にもとづいている。
それはまず「みせしめ」であって、公開処刑(市中引き回し・はりつけ・さらし首など)と憎悪心の残虐な暴力性への転換を求めるものであった。つまり、刑罰と国家の残虐性の承認である。
[ これが主題ではないが、最近公刊された芹沢一也著『狂気と犯罪』(2005.講談社+α新書)は「近代ニホン」の警察・行刑・刑罰の思想史を考える上で貴重な仕事である。タイトルはいささかセンセーショナルだが、内容は精神障害者とその「周縁」についてくわしい。 ]
*
「家族の連座制」について、長崎の事件で、当時の大臣が「市中引き回しの上死罪」云々といったのは、『鬼平犯科帳』レベルの江戸時代の発想だが、被告の家族に対するサンクション(社会的制裁)は、事実行われていることだ。
たとえば、宮崎勤の場合は、父親が自殺したし、家族は破壊された。同時に被害者の家族もこわれていったという。
宮崎勤については、大塚英志のとくに<「宮崎勤」は誰にもわからない(『夢のなか』宮崎勤著)>を、それが入手できなければ<「宮崎勤」と「私」の不在>、<宮崎勤と批評される「主体」>(いずれも『戦後民主主義のリハビリテーション』所収)、または対談「エヴァンゲリオン・アンバウンド」(『だいたいでいいじゃない。』)を参照されたい。
オウム真理教・岡崎被告の死刑
4月7日、最高裁は一,二審の死刑判決を支持、上告を棄却した。オウム真理教事件ではじめての死刑確定となった。
坂本弁護士一家3人の殺害と元信者の男性殺害実行犯という。坂本弁護士家族の遺族が
「事件の真実が究明されないまま、犯人の刑が確定していくことは残念でならない」こと。
また事件から15年がたっての判決に、なぜ、裁判が長期にわたるのか理解に苦しむとコメントを寄せた。
(参考・中国新聞2005・4・8)
「名張毒ぶどう酒事件」再審無罪!
2005年4月5日、名古屋高裁は、「名張毒ぶどう酒事件」の死刑が確定した奥西被告の第7次再審請求審で、「再審開始の決定」と「死刑執行停止」の決定をしたことが伝えられた。(参考・中国新聞 )
事件は、1961年3月、ぶどう酒に農薬が混入され、女性5人が死亡。1964年、津地裁で無罪判決となったが、69年名古屋地裁で逆転有罪。1972年に最高裁で死刑が確定していた。
冤罪(えんざい)事件では、死刑確定後に再審が決定したのは、過去4件。いずれも無罪判決が出ている。
○免田事件 1948年 1983年再審無罪
○財田川事件 1950年 1984年再審無罪
○松山事件 1955年 1984年再審無罪
○島田事件 1954年 1989年再審無罪
いずれも警察の、ときには拷問までした取調べや、ずさんな証拠鑑定で、若い容疑者が犯人に仕立て上げられたもの。ほかにも、狭山事件など再審請求が却下されつづけている事件もある。
死刑が確定した1972年以来、33年が過ぎた。
無罪を訴えつづけ、「年齢からして最後の機会」と死刑囚と弁護団、支援者たちは「今度こそは」と強い期待を持って、とはいってもこれまでの経過からきわめて不安な気持ちで待っていた。
私は、最初に弁護団が、泣きながらインタビューを受けていたのをみてもらい泣きした。
奥西さんの長生を願うばかりだ。
死刑の根拠そのものへの・・・
最高裁での死刑確定事件の再審決定は、わずか、5件目。「戦後」である。つまり「戦前」は再審自体がありえなかった。ニホン近代の冤罪事件がどれほどあったか。
いったいどれほどの人たちが無罪を叫びながら、死刑になったか。
いや、叫ぶことも許されずに、死刑になったか。
考えるだけで、死刑制度のあやまちをおもわずにはおれない。
この冤罪も死刑廃止の論拠の一つである。
さて、同じ今年3月、お隣の韓国ではじめて「死刑制度廃止法案」が審議入りしたと伝えられた。
(中国新聞05・3・15)
法案の提出者代表、ユ・インテ(柳寅泰)さんは、1974年、60年代の民主化運動で死刑判決を受けたことがある国会議員(ウリ党)。
<死刑は人間の尊厳を損なう残虐な行為で、冤罪で死刑を執行した場合、取り返しがつかない>
<死刑が犯罪抑止になるとの主張もあるが、国連の研究報告も「死刑が犯罪抑止に効果的との証明はない」と結論づけている。韓国の裁判官の35%が1回以上の誤審経験を持つとの調査もある。>
と述べていた。
まさに、死刑は権力の恣意の下にある。(つづく)
拷問と自白
多くの冤罪事件は、自白の強要、誘導、拷問による虚偽の自白によってでっち上げられている。
最近では、1ヶ月前の「横浜事件」の再審決定がなされたのが記憶に新しい(今年2005年3月10日)。
「横浜事件」(「改造社」弾圧事件)の記事の一部を引用しておきたい。
<多数の雑誌編集者らが治安維持法違反の罪に問われ、戦時下最大の言論弾圧事件とされる「横浜事件」で、有罪判決を受けた元被告5人の遺族が裁判のやり直しを申し立てた第3次再審請求に対し、東京高裁は10日、再審開始を認めた横浜地裁決定を不服とする検察側の即時抗告を棄却する決定をした。中川武隆裁判長は「元被告らは取り調べ中、拷問を受け、やむなく虚偽の疑いのある自白をした」と認定。有罪判決の事実認定には疑いがあると判断した。 >
<再審を請求しているのは、中央公論社の出版部員だった故・木村亨さんの妻まきさん(56)ら5人。亨さんら元被告5人(いずれも故人)は、45年8月14日に日本が御前会議でポツダム宣言受諾を決めてから、治安維持法が勅令で廃止された同年10月15日までの間に有罪判決を受けた。
>(朝日新聞)
元被告の5人はいずれも亡くなっている。実に60年という歳月が過ぎたのだ。
これは、軍国主義下の「治安維持法」によるでっち上げ事件だが、同法の廃止寸前で有罪判決を受けた。
拷問と自白による冤罪事件は、それ以降なくなったわけではないことは周知の事実だ。
実は、こんにちまで、ニホン警察の構造自体に「自白」優先の体質は温存されている。
それは、明治になってつくられた非近代的「ニホン警察」は、江戸時代の行政警察、司法と刑罰を根本的に受け継いできたからである。
党派の関与
なお、名張事件、横浜事件ともある政党がからみ、web上でもセクトっぽい説明がある。長く支援しつづけるためには、それなりの組織がないと支えきれないという事情がある。
問題は党派性が関与するわけのものではないこと、まして党派による囲い込みは避けるべきだということを付け加えるほかない。
治安維持・別名・セキュリティ
江戸時代、いかに物的証拠が揃っていても、自白がなければ有罪とはならなかった。江戸時代、取調べとは拷問だったといってもいい。そうした拷問道具は各地に残っている。
逆に言えば、自白さえあれば、必ずといっていいほど有罪となる。そのため「自白」させることが最優先となる。
冤罪事件は、自白に基づいて証拠を作る、という倒錯したかたちででっち上げられるのである。
狭山事件が、まったくこの典型である。
そうした傾向を、警察と検察は、いまでも引きずっている。
こうした警察と司法の基本構造を変えることのないまま、裁判員制度を導入するのは、いっけん、司法への市民参加に見えるが、刑務所の民営化、地域の民間「警察」化など、行政の責任を民間に転嫁するおそれがある。
治安維持(国家社会のセキュリティ)は、警察化した民間組織や密告制度を持つ方が効果的だし、コストも安い。警察国家は、そうした相互監視や密告政治によって成立する。